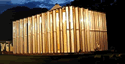JR「松島海岸」駅を降りると、浜風がかすかに吹いている。ひと息ついてロータリーに出ると、遊覧船のりばからアナウンスが聞こえてくる。
正面には、等間隔で植えられた松の向こうに、ちらちらと水面をすすむ遊覧船の姿が見える。ここにはおよそ、被災地という印象がない。
仙台から北へ向かう仙石線は、ここから矢本駅までが不通となっている。矢本行き代替バスの戸口に立つと、中に立つ係員の顔がちょっと曇った。
「いま満席になったんだわ。次は1時間後。わるいけど、待っててけれ」。
--立ったままでいいので、乗せてもらえませんか。3時まで石巻に着かないと、人を待たせてしまうので。
「いやぁ、それはできねんだ。すまねっけど、ちょうどいっぱいになっちゃって」。
--じゃあ、ほかに移動の方法はありますか。
「1時間待ってもらえねべか。あとはハイヤーだな」。
待ち合わせは午後3時。次のバスを待てば、石巻到着は4時になってしまう。
「なに、人と会う約束でもしてるのかい」。
会話を聞いていたのだろう。誘導のおじさんのひとりが、横から声をかけてきた。
--そうなんです。
「じゃ、石巻まで乗せてっちゃる。すまないけど、ちょっと待っててけれ。あと5分だからよ、あそこさ座ってさ」。
あっけにとられて、状況がよく飲み込めない。石巻は、ここから車で1時間以上走らなければならないはず。すまないけど、というが、助けてくれる、ということだろうか。とにかく、駅を背に、観光案内所横のベンチに腰をおろした。
ふたたび遊覧船の姿と、乗船のアナウンス。そうして10分ほど待っただろうか。おじさんが詰め所から出てきて、
「さ、行くべ。待たせてすまなかったね。おらの小さい車で窮屈だけど、かんべんしてくれ」。
-- あの、どこまで連れて行ってくれるのでしょう。矢本まで……?
「いいのさ。おれも石巻から来てっからさ」。
そういって、おじさんは軽自動車の助手席をさっと片付けた。
「はい、どうぞ。あんた、困ってたみたいだからさ。‘しま’さ、なんしに来たんだ?」。
松島のことを、地元の人たちは‘しま’と呼ぶらしい。ここから1時間。石巻は震災で大きな被害を受けた土地だ。おじさんと、なにをどう話したらよいのだろう。京都から来た、と告げると、
「なに、視察かい。ボランティアかい? ご苦労さんだね」
おじさんは、石巻市内の海のちかくで、生花店を営んでいたという。
「家も花もなんも、全部流されてしまったのさ。いやぁ、したけどね、命があるだけ、ありがたい。あったら波さ来たら、なんもかんも、だめになるわ」。
代替バスの誘導をしている男性は、みな中高年で、4人ほどいただろうか。全員が、家をながされ、仕事を失い、朝6時の始発から午後2時まで、乗客誘導のアルバイトに来ているのだという。
「仕事があるだけ、いいほうさ。おらがいちばん遠くから通ってんだ。んだ。ガソリン代もばかになんねっけど、家でじっとしてるより、いいべえ。‘しま’はうっそみたいに何ともないんだ。いま走ってるとこだけ見たら、それこそ、なんにもなかったように見えるべ」。
確かに、車窓からは稲が、うっすら黄色い風に揺れている。
「でも、見てみれ。そこさ、仮設あるべ。あらぁ、海のそばさ住んでたモンだ」。
車は、国道沿いを走る。助手席の窓の外には、時おりブルーシートのかかった家や商店が見える。おそるおそる、聞いてみる。
--ご家族はご無事だったのですか。
「ん、無事だ。おっかちゃんがおらの店ん横の駐車場さ、いたもんだから ‘津波さ来たぞ!’って叫んで。いっしょに何人かいたんだ。だからよ、まとめて車で逃げろって。したらば‘大丈夫だべ’っていうもんだから‘だめだ、逃げろ!’って、言ったんだ……3日だ。おっかちゃんや、矢本にいる息子夫婦や孫と、連絡ばとれないもんで、水(津波)さ飲まれっちまったかと思ってたんだ」。
--みんな、べつべつの場所で避難していたんですね。
「そういうことだ。おっかちゃんはおらより後さ逃げたから遅かったんだけど、流れてきた丸太の上さ車が載って、水かぶらなくてすんだんだ。そうやって、助かったのさ……ん、運命だね。運命としか言いようがないね。
おらさ、車で途中までにげたもんさ、そしたら(車の)中さ水入ってきたもんだから、(車を)ぶん投げて避難所まで走ったんだ。みんな、あったら波さ来るとは思ってなかったのさ。おらも店にいて、パソコンがいたましくて、ほらよ、棚の上のほうさあげようと思ってたら、若いモンが来て‘津波くるぞ〜’って叫ぶんだ。だから、急いで逃げたんだ。おっかちゃんに声かけてさ」。
「みんな、警報ば出てても、まさかって思ってたんだ。慣れっこになってて。家から外さ出て来ねんだ。そうやって、たぁっくさんの人間が、あっちゅう間に飲まれっちまったのさ」。
3.11当日は、連休前の金曜日。卒業式を見込んで、おじさんは、朝早く仙台の市場へ出かけ、たくさんの花を仕入れてきたのだという。
「いや、たくさん仕入れねばよかったと(今になって)思っても、もうどうしようもねえ。こないだ、やっと支払いさ済ませてきたんだ。払わんわけにはいかねっしょ」。
時の断片をつなぐように、おじさんの話はいったり来たりする。
「京都の人らはさ、(この地震は)どう伝わってるんだい。おらのおんちゃん(兄さん)さ、京都にいて、もう80さなるんだけど、いいっていっても、心配だからって見に来たべ。(まちの様子を見て)びっくりしてたぁ」。
「おらのおっかちゃんさ、若いとき京都にいて、いまでも行きたいって言ってんだ。年金で暮らして、12年前に建てた家と店を失って。んだ。残ったのは、借金だけだ。でもよ、いのちがあっから、なんとでもなるべ。そう考えないとな」。
おじさんはいま、石巻の山の手で、夫婦ふたり仮設住宅に暮らしているという。義援金は一度、支払われただけ。
「おらがアルバイトしてっから、ふたりで何とか食ってけるのさ」。
土地をなんとかしたくても、区画の立ち入り規制がかかって、なんともできない。
「いまちょうど、国会さやってるけど、国も、県も、市も、らちがあがねんだ」。
復興の階段は、誰の手で積みあげられていくのだろう。誰かがはじめないと、先の暮らしを、考えることもできない。しかし、まだその一歩が、踏み出せない。
おじさんの息子さん夫婦も、矢本で生花店を営んでいた。店舗は水をかぶったが、建物はなんとか残ったそうだ。
「でもまだ、商売はできねぇ」。
声が少し、小さくなったように思う。おじさんの頭のなかにあって、つぎつぎに呼び覚まされる記憶の流れに、ただうなずくしかない。
「人さ使われたことなんて、いままでなかったんだ。ん、初めてだ。でもよ、楽な仕事だぁ、今は。駅から人がやってきて、ただそれをさ、こっちですよって言ってよ。この歳になって人さ使われてさ。気楽だぁ。ん、なんでも社会勉強だな、いくつになってもよ。ほら、おら、ダンスやってんだ。んだ、あれだ。そう、社交ダンス。(ペアの)相手は山のほうさ住んでたから、無事だった。地震のあと‘はえ(早)ぐ来い’ってよ、仲間も言ってくれてんだども」。
--衣装も靴も揃えていたんですね。あの、フリフリしてる……。
「そ〜だ! あの服も靴も、ぜえんぶ、流されちまってよ。ダンスは楽しいぞお。お姉ちゃんもやってみろ。いいもんだ。いやいや、もっとだ。20年以上前からやってんだ。音楽聞いて、身体動かして、汗かいたら気持ちイイぞお」。
「なんでもね、やってみることだ。やってみないうちからやンだ、ダメだっていってたら、それこそダメだ。ほら、だんなさん誘ってさ、ダンスやってみな。あんたのお父さん、何年生まれだ? 昭和13年? おら、16年だ。いま70だ。あと10年は生きるべ、せいぜい愉しまないとな。だってよ、人生、一度っきりだ。一回だけだぁ」。
「さ、ちょうどいい時間だ。もうすぐ駅さ着くからよ。3時に間に合ったべ。えがったな」。
京都に戻ってから何かお礼がしたくて、別れぎわに住所をたずねた。おじさんは何も言わない。
「ほら、いま仮設(に住んでいる)だから、おら住所なんて知らねんだ。何もいらねって!」。
察してか、ほんとうに知らずか、ちょっとだけ、間があった。
助手席から見ていると、おじさんがなんだか、とても懐かしい気がした。まったく私的なことだが、宮城と福島の血が半分ずつ入っている父親と、おじさんが重なって見えた。偶然というより、当然のことかもしれない。商売で身を立てていたところも、相手に気遣いをさせまいと、ぶっきらぼうに言い放つところも。そして、何があってもぜったいに「疲れた」「ゆるくない(暮らしが楽でない)」と口にしないところも。
少しだけ寂しそうに、過ごした人生の、静かな光を放って、下まぶたをくっともちあげて笑う、目のあたりも。
石巻駅に到着したのは、午後3時5分前だった。
「さ、着いたぞ。だんなさんと、仲良くね」。
口もとの歯が、2本ぶん、欠けている。こんなところまで、父親と似ている。せめて、と、別れぎわに握手をした。かっしりとした、それでいて、少しやわらかい感触の手のひらだった。